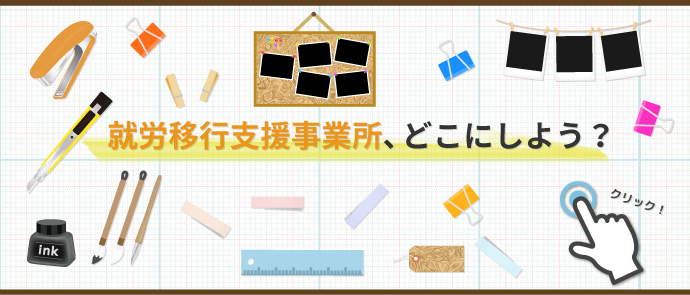「ついカッとなって怒鳴って後悔…」
「怒りを抑えて苦しくなった…」
誰しも一度はこんな経験があるはず。
「怒り」で人間関係が壊れたり、仕事にも影響したり…何かと扱いづらい感情ですが、人間にとって必要な感情のひとつです。
大切なのは「怒り」に振り回されず、上手に付き合うこと!
「アンガーマネージメント」は、怒りの感情と上手に付き合うための心理トレーニングです。
アンガーマネージメントで人生をもっと楽に生きてみませんか?
第21回は、「アンガーマネージメントを実践する①」の続き、「アンガーマネージメントを実践する②」を解説していきます。
目次
アンガーマネージメントを実践する②
前回に引き続き、「実生活に役立てるアンガーマネージメント」として、場面別の実践方法とコツをご紹介します。
自分が怒りを感じた時、他人に怒りをぶつけられた時の参考にしてください。
【3】SNSとは適度な距離をとる
インターネットの掲示板やSNSで、ある発言に反論や非難が殺到して、収集がつかなくなる状態を「炎上」と言いますが、反論や非難というより、実際は目も当てられないような罵詈雑言が飛び交っている場合もあります。
普通の社会人として生活をしていて、悪意をぶつけるようには見えない人が、ネットでは人が変わったようになるのがインターネットの一面でもあります。
匿名掲示板に限らず、会社名や実名を明かすSNSでも同様の暴言が多く見られます。
怒りにとらわれると時間の感覚がなくなる…!
このようにネット上で暴言が繰り広げられてしまうのは、インンターネット空間では、相手との距離感がなくなってしまうことが原因とされています。
距離感が狂うと、人はおかしな行動をしてしまいます。
例えば、結婚40年を超す70代の夫婦間で、40年前の夫の浮気が夫婦喧嘩のネタになるようなことが起きたとすると、何かの拍子に怒りにとらわれると、時間感覚がなくなってしまうため、40年前のことが昨日のことのように問題になってしまいます。
これと同様、ネットでは距離感が失われてしまいます。
インターネットが一般に広がる前は、テレビの出演者は雲の上の存在でしたが、最近はSNSで著名人を身近な相手と感じる人も増えて、その結果、簡単に悪口や非難が書かれてしまうのです。
そのような被害は著名人に限らず、友人のSNSに自分の悪口が書かれていたり、
自分が書いた記事に悪意のある書き込みをされるなど、一般の方でもあることです。
気になるならSNSとの距離を取りましょう。
また、不快な情報にわざわざ近づく必要はないので、やめてしまうのも一つの手段です。
何を書かれても目にしなければ書かれていないのと同じですよね。
【4】パワハラをしない・されないためには
突然、機嫌が悪くなる人が職場にいるとやっかいですが、それが上司ならなおのこと。
突然、大声で怒られたり、イライラした態度をとられると、どうしていいのか分からなくなりますよね。
当然、大きなストレスを感じてしまいますが、このような人とうまく付き合うには、まず相手をよく観察してみてください。
観察するポイントは、その人の物事を見る際の心のメガネ・フィルターです。
「なぜこの言葉に反応するのか」「月曜日の午前中はイライラしている」など、何らかの傾向が見えてきたらしめたものです。
相手の「べき」が分かれば、それに触れないように対応できます。
同じく、機嫌が悪くならないパターンがありそうなら、それを再現してみるのもいいでしょう。
「あの二人はぶつかりやすいけど、間にAさんが入ると緩衝材になるようだ」というような対応策が見つかるかもしれません。
また、相手がルールのブレる人、いわゆる気分屋なら、できるだけ受け流すようにしてください。
アンガーマネージメントは、いうなれば合気道と同じ。
自分から積極的に責めるよりも、相手の怒りを受け流していくことを優先しましょう。
パワハラの知識を身につけよう
最近は、職場でのパワーハラスメントが深刻な問題になっていますが、どんな言動がパワハラかが分かりづらく、暴力などは別にして、精神的なものはケースバイケースで、定義があいまいです。
実際、パワハラをする側がパワハラと認識する案件は17%弱、対してパワハラされる側は54%弱と、実に3倍ほどの開きがあり、パワハラ問題の難しさを表しています。
だからこそ、何がパワハラで、何がパワハラでないかの「知識をつけること」が、パワハラしない・されないための第一歩になります。
次回、「アンガーマネージメントを実践する③」、へ続く