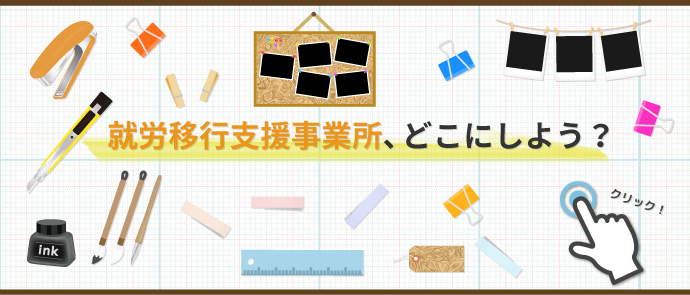前回の記事⇒「発達障害とは?① ~代表的な3つの障害の特徴~」はこちら
今回は、発達障害のひとつ、ADHD(注意欠陥多動性障害)の特徴・症状について詳しく見ていきます。
ADHD(注意欠陥・多動性障害)は、英語で Attention-Deficit Hyperactivity Disorder の略で、不注意(集中力がない)、多動性(じっとしていられない)、衝動性(考えずに行動してしまう)、の3つの症状がみられる発達障害のひとつです。
目次
ADHDの主症状は主に3つ
上述したように、ADHDの主な症状は「不注意(注意欠陥)」「多動性」「衝動性」の3つがあげられます。
- 忘れ物が多く、物をすぐ失くしてしまう(不注意)
- 気が散りやすい(不注意)
- ひとつの事を長時間集中してやることが苦手(不注意)
- じっとしているのが苦手(多動性)
- 退屈な事に耐えられない(多動性)
- 落ち着きがなくせっかちで、先走りがち(多動性)
- 思い立ったらすぐに行動したくなる(衝動性)
- 順番を待つのが苦手(衝動性)
- 相手の話を最後まで聞いたりすることが不得意(衝動性)
これらの症状は、子どもの頃から、2つ以上の場所(学校や家庭、職場)などでみられ、そのために生活に大きな支障が出ていることがADHDと診断される条件となります。
上記のように、診断基準となる条件は、小学校高学年頃までの子どもによくみられる症状が中心となっていますが、症状が見過ごされて大人になるケースもあります。
大人のADHDはまだ一般的にあまり認知されておらず、また、国際的に認められた診断基準が存在しないため、誤解を受けやすい事があります。
ADHDの3つのタイプ
注意力に欠ける・落ち着きがない・待てないなどが主症状のADHDですが、「静」と「動」のタイプに加え、それらが混合したタイプもあります。
- 不注意優勢型
- 多動・衝動性優勢型
- 混合型
不注意優勢型
このタイプはぼんやりしていたりケアレスミスが多いなどの特徴があり、要領が悪く、普通の人にはごく当たり前のルーティンワークなどが苦手だったりします。
このタイプの人がアスペルガー症候群の特徴を持っていると、同じ様にみえても何かに没頭して過集中になるために、作業が進まなくなる事が多いです。
- ケアレスミスが多い
- いつも探し物をしている
- 整理整頓が苦手
- すぐに気が散る
多動・衝動性優勢型
落ち着かず、イライラしやすい一方、退屈な話や作業のときにはすぐに飽きてしまう傾向にあります。
地道で継続的な努力が苦手で結果を求めるのを急ぎ、今の楽しみを求めがちなので興味がすぐに移ろってしまいます。
- いつも落ち着きが無い
- 順番が待てない
- おしゃべり
- せっかち
どちらも目立つ混合型
不注意優勢型と多動・衝動性優勢型は混合する事も多く、どちらか一方に分類されることができない事も多いのです。
アスペルガー症候群とADHDはどのように違うのか?
症状的には一見同じ様にみえるADHDとアスペルガー症候群。
厳密には違う症状なのですが、合併する事もある為完全な線引きは出来ない事もあります。
中核となる症状が違う
アスペルガー症候群とADHDでは中核となる症状が異なってきます。
アスペルガー症候群は、人との関わりがメインの症状。
ADHDは、集中力や行動、感情のコントロールなどの前頭葉の問題がメインの症状です。
よく似ている症状でも、厳密には違いがあります。
例えば、一度これと決めるとそれをがっつりやれるが、逆にそればかりになってしまう事が多いアスペルガー症候群の人に対し、やると決めた事をなかなか続けられないのがADHDの人であったりなどわずかな違いが見られます。
アスペルガー症候群とADHDの違い【比較表】

大人のADHD
ADHDで現在広く用いられている診断基準は、12歳になる前からその症状がみられるものとされています。
また、これまでADHDの症状は、年齢を重ねると治まる傾向にあるとされてきましたが、最近の研究では、約60%の人に成人期にも症状が残ると言われています。
大人のADHDは、多動性が弱まり、不注意が目立つ傾向にあるようです。
現在のところ、国際的に認められた大人のADHDの診断基準はまだ存在しませんが、エドワード・M・ハロウェルら(医学博士・精神科医)は、以下のような試案を作っています。
- 1.力が出し切れていない、目標に達していないと感じる
- 2.計画、準備が困難
- 3.物事をだらだらと先送りしたり、仕事にとりかかるのが困難
- 4.たくさんの計画が同時進行し、完成しない
- 5.タイミングや場所、状況を考えずに頭に浮かんだことをパッと言ってしまう
- 6.常に強い刺激を追い求める
- 7.退屈さに耐えられない
- 8.すぐに気が散り、集中力がない。半面、時として非常に集中できる
- 9.しばしば創造的、直感的、かつ知能が高い
- 10.決められたやり方や「適切な」手順に従うのが苦手
- 11.短気で、ストレスや欲求不満に耐えられない
- 12.衝動性
- 13.必要のないのに際限なく心配する
- 14.不安感
- 15.気分が変わりやすい
- 16.気ぜわしい
- 17.耽溺の傾向がある
- 18.慢性的な自尊心の低さ
- 19.不正確な自己認識
- 20.ADD(注意欠陥障害)または躁うつ病、鬱状態、薬物中毒(アル中を含む)あるいは衝動や気分が抑制しにくいなどの家族歴がある
こうした症状がある人が、全てADHDというわけではありません。
ADHDに似た症状を示す障害は他にもあるため、診断を下すには他の障害や病気でないことを確認する必要があります。
また、ADHDは自閉症スペクトラム症など、他の発達障害や精神疾患、身体疾患が併発していることも少なくありません。
治療効果や将来に影響を及ぼす可能性もあるため、併存症の有無も適切に診断する必要があります。
ADHDを含めた発達障害では、「その人の特性により生活に支障が出ているか」が問題です。
言い換えれば、特性はそのままでも暮らし方を見直し、生活する上で支障がなければ障害ととらえる必要はなくなります。
実際、ADHDの特性を持ちながら、社会で活躍している人は大勢います。
「治す」のではなく、「特性を活かし豊かに生きる」。
その補助として医療を利用する。
そんなイメージで自分の特性と付き合っていく方法を見つけていくことが大切です。
次回は、発達障害のひとつLD(学習障害)の特徴について、より詳しくみていきます。
参考:
司馬理英子,「ササっとわかる『大人のADHD』基礎知識と対処法,講談社,2011/10/25
司馬理英子,のび太・ジャイアン症候群5 家族のADHD・大人のADHD お母さんセラピー,株式会社主婦の友社,2002/01/10
日本イーライリリー株式会社,大人の発達障害 すべては自分の特性を知ることから,2016/02